富士宮やきそばの特徴

蒸し麺
一般的なやきそばの麺は、蒸した後にゆでていますが、富士宮やきそばの麺は、「蒸し麺」の製法で作られています。
蒸した後の麺を湯通し(ボイル)するのではなく、ほぐして休息に冷やし、油で表面をコーティングすることで、水分が少なく、コシのある麺が出来上がります。この食感こそが、富士宮やきそばに欠かすことのできない大きな特徴となっています。
富士宮やきそばは、富士宮市内の製麵会社である「マルモ食品工業」「曽我めん」「叶屋」「さのめん」のいずれかの蒸し麺を使用して作られています。

肉かす
富士宮やきそばの具材として欠かせないのが、豚肉の背油からラードを絞った後に残る副産物である「肉かす」。かつて高価な豚肉を具材として使用できなかった時代、代用品として使われたことが始まりと言われています。旨み成分が凝縮された肉かすは、蒸し麺との相性もぴったりです。
細かく刻んで麺全体に旨みを染み渡らせる店や、荒く刻んで肉かすそのものの食感を楽しませる店など、お店によって活用方法はさまざまです。

だし粉(削り粉)
仕上げにやきそばに振りかけるのが、イワシを主に利用しただし粉(削り粉)です。市内では単純に「こな」と呼ばれることもあります。
富士宮市からさほど離れていない、駿河湾沿いの由比、蒲原の漁港等では、古くから鰯の削り節が生産されており、この製造中、また輸送中に振動等で粉末となって商品化できなくなったものを「だし粉」と呼んで富士宮やきそばの香りづけに使ったのが始まりと言われています。
肉かすの旨みとだし粉の香りのハーモニーは、クセになる味わいです。

ソース
歯ごたえのある麺によくなじむのが、香ばしいソース味。熱々の鉄板から聞こえるジュワっというあの音が食欲をそそります。
ウスター系のソースを利用する店舗が多く、富士宮やきそば専用に開発されたソースを利用するお店や、独自にブレンドをしているお店など様々です。
~このほかにも富士宮やきそばならではの様々な魅力があります~

紅しょうが
富士宮やきそばに彩と香りを添えるのが、紅しょうが。
特にこの地域では赤紫蘇で生姜を染めてつくったものを使用することが多く、一般的な紅しょうがよりも、色味が赤紫(ピンク色)がかっています。
生姜と紫蘇の香りがアクセントになり、香ばしいソース味のやきそばの箸休めにも、混ぜて食べても美味しくお召し上がりいただけます。
※紅ショウガの「ミカチャン」は秋本食品株式会社の登録商標です。

キャベツ
富士山麓に位置する富士宮市では、富士山の湧水、火山灰を含んだ水はけのよい土壌によって豊富な野菜が育まれています。シャキッとした歯ごたえのおいしい高原キャベツは、みずみずしく甘さもあり、富士宮やきそばには欠かせない名脇役です。

富士山の湧水
富士山の湧水は富士宮市ならではの自然の恵み。麺の製造に使われるほか、市内の店舗では調理時に麺を蒸らして麺の硬さを調節するのにも役立てています。
これらを基本素材とし、お店によって、ネギ、イカ、卵など、トッピングも様々です。
クラシックな富士宮やきそばを味わった後は、ぜひまちあるきをしながら、食べ比べをしてみてはいかがでしょうか。
※「富士宮やきそば」の名称を使用して販売をされる場合、株式会社プロシューマーの研修を受講、商標利用契約を締結する必要がございます。
詳しくは【登録商標:富士宮やきそば】のページをご確認ください。
富士宮やきそばのあゆみ
"Let there be YAKISOBA" はじめに「ヤキソバ在れ!」と神は言われた、そんなわけはないが私が物心ついた頃にはすでに富士宮の町じゅうにソースの香りが漂っており、その「ヤキソバ」は存在していた。
(渡辺英彦(2007)ヤ・キ・ソ・バ・イ・ブ・ル 面白くて役に立つまちづくりの聖書 静岡新聞社)
戦後間もない頃から駄菓子屋さんなどで提供
富士宮市では戦後間もない頃から食されてきた、独特のコシをもつヤキソバ。特徴的な蒸し麺に加えて、ラードを製造した後に残る「肉かす」と、主にイワシの削り粉「だし粉」を特徴とする一品ですが、駄菓子屋などで提供されていたこのヤキソバは、富士宮の市民にとってはあまりにも身近な味として浸透していたために、長い間市民のみぞ知る食文化として富士宮市内にひっそりと息づいていました。
富士宮やきそば学会立ち上げ
2000年、そこへ脚光をあて、富士宮のヤキソバをまちおこしに活用しようと立ち上がったのが、富士宮やきそば学会です。富士宮やきそば学会会長(兼株式会社プロシューマー代表取締役社長)の故渡辺英彦は「遊び心」をキーワードに、「ミッション麺ポッシブル」「三者麺談&三国同麺」「麺財符」等オヤジギャグを駆使したまちおこし活動を展開。食による地域ブランド確立および活性化戦略における日本のまちおこしの第一人者として、全国にまちおこしの活動の輪を広げていきました。
「B-1グランプリ」でゴールドグランプリを受賞

そして富士宮やきそば学会は2006年、2007年の2年連続で、地元の料理を通じて地域をPRする日本最大級のイベント「ご当地グルメでまちおこしの祭典!B-1グランプリ」でゴールドグランプリを受賞。これも大きな推進力となり、観光客やマスコミから広く着目されることになった「富士宮やきそば」は、地元のみならず全国から愛される「地域のブランド」として成長を遂げていきました。
「富士宮やきそば」のブランドを守る商標管理運営会社設立

「富士宮やきそば」が広く知れ渡るのと同時に、一方で残念ながらまったく異なるヤキソバを「富士宮やきそば」と称し販売されるケース等が現れました。こういった「富士宮やきそば」のイメージの損壊は、長い目で見ると地域自体のイメージが崩れることにもつながる恐れがあります。そこで2008年、「富士宮やきそば」のブランドを守る商標管理運営会社として、渡辺英彦を代表取締役社長とする株式会社プロシューマーが設立されました。また、最もスタンダードな富士宮やきそばをご提供したいという観点から、お宮横丁内のアンテナショップの運営もまた、弊社が担当させていただくこととなりました。町おこしのプロフェッショナルである富士宮やきそば学会と連携を取りつつ、弊社ではこれからも「富士宮やきそば」によって培われた地域のブランドを守り育てていきます。
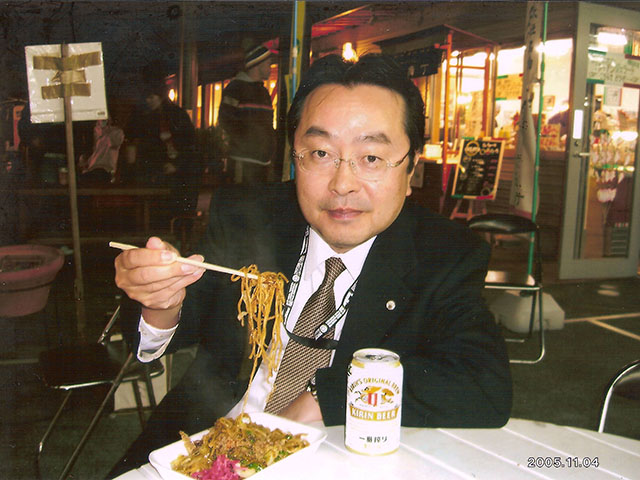
2018年、渡辺英彦はがんとの闘病の末惜しくもこの世を去りましたが、誰よりも遊び心を大切にし、言葉のもつ力を信じ、多くの仲間を巻き込み、巻き込まれながら精力的に活動した彼の想いは、今もなお我々の中に生き続けています。
